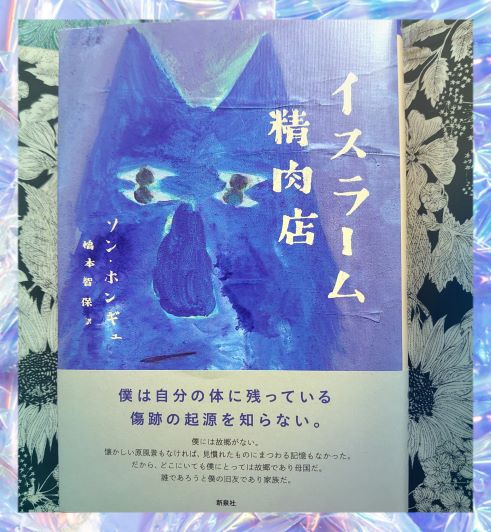イスラーム精肉店
『イスラーム精肉店』ソン・ホンギ著 橋本智保訳 新泉社
韓国でロングセラー。英語版とトルコ語版も翻訳出版された話題作
紹介文
〈僕は自分の体に残っている傷跡の起源を知らない。〉
「僕には故郷がない。
懐かしい原風景もなければ、見慣れたものにまつわる記憶もなかった。
だから、どこにいても僕にとっては故郷であり母国だ。
誰であろうと僕の旧友であり家族だ。」
その日、僕はこの世界を養子に迎えることにした——。
朝鮮戦争の数十年後、ソウルのイスラーム寺院周辺のみすぼらしい街。
孤児院を転々としていた少年は、精肉店を営む老トルコ人に引き取られる。
朝鮮戦争時に国連軍に従軍した老人は、休戦後も故郷に帰らず韓国に残り、
敬虔なムスリムなのに豚肉を売って生計を立てている。
家族や故郷を失い、心身に深い傷を負った人たちが集う街で暮らすなかで、
少年は固く閉ざしていた心の扉を徐々に開いていく。
「僕はハサンおじさんに訊きたかった。
僕の体にある傷跡は、なにを守ろうとしてできたものなの?
僕にも守るべき魂があったの?
もしあったとしたら、僕の魂はなぜいまも貧しいの?
なぜ僕は肉体も魂も傷ついたの?
僕の魂は肉体を守ってやれなかったし、肉体は魂を守ってくれなかった。
ということは、僕の魂と肉体はずっとばらばらだったのだろうか——。」
ー---新泉社 webサイトより
またも韓国文学
最近、第〇韓流ブームで韓国ドラマが話題だが、韓国ドラマと韓国文学は真逆に位置するように思う。
それは、韓国文学は多くを語らない。読者の余白を大切にする。
成功ストーリーではなく、底辺を這うような苦しい生活の物語が多い。
これらは、映像では「映え」ない。
色に例えるとグレーなのだ。
そこに人と人の不器用な温もりがある。
この「ぼく」がとても哲学的で、心の声がとても響いていくる。
まったく希望のない街で、力強く生きて欲しい。
なぜ、韓国文学はこんなにも人の心に響いてくるのだろう?
明るい話ではないのに、明るい要素なんてないのに、読み終わると頑張ろうと思えてくる。
不思議なカテゴリーを確立したのではないかな……
韓国文学は、沼である!